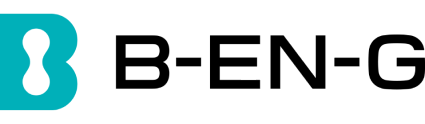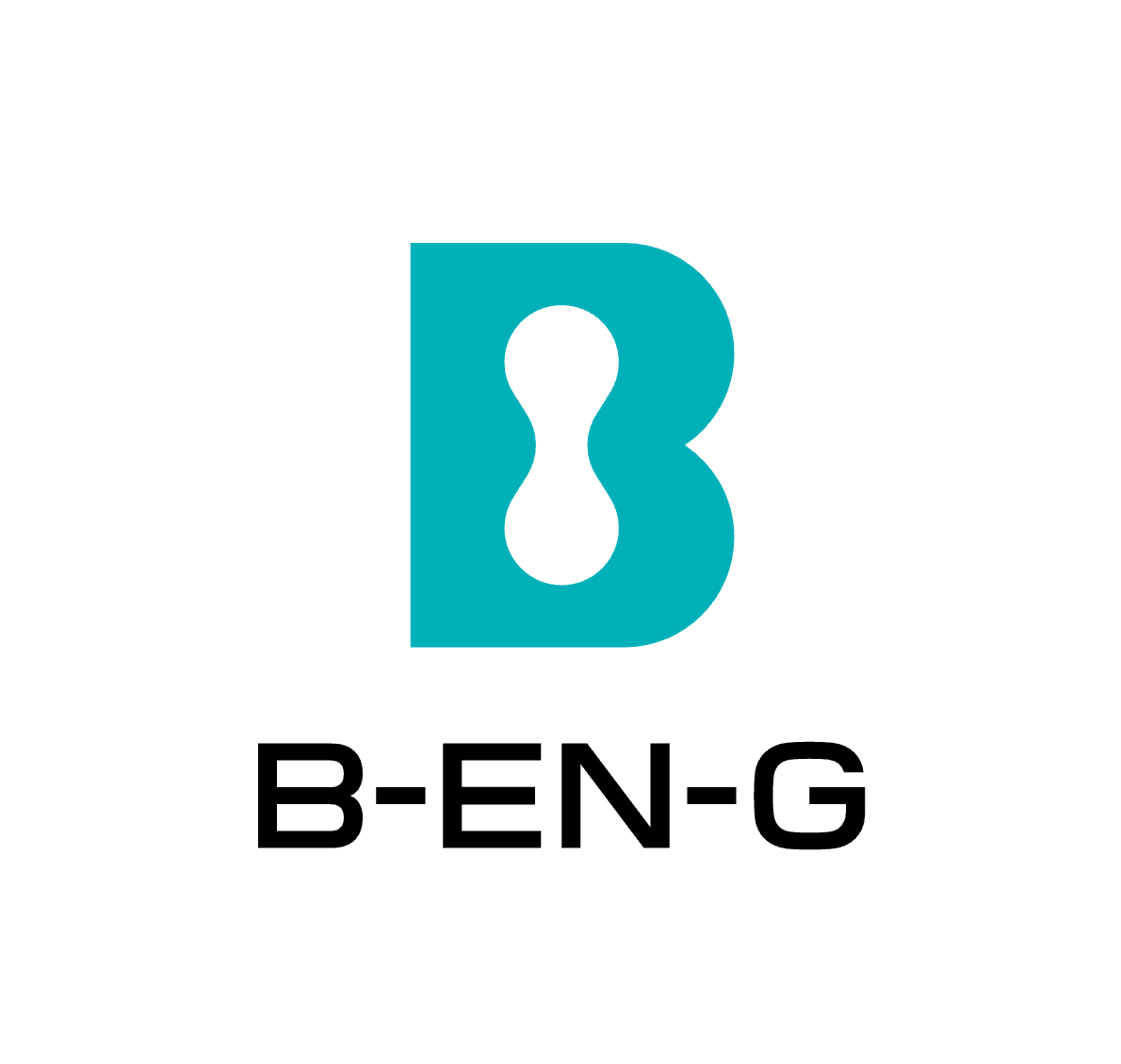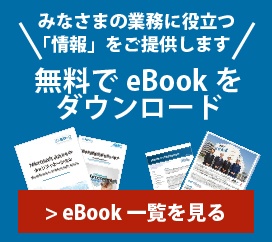BE:YOND 2025 セッションレポート「デジタルソリューション基盤整備と“非競争領域の標準化”により推進する三菱重工のDX」
三菱重工業株式会社は、"DXでデジタル技術とものづくりを「かしこく・つなぐ」"をコンセプトとしてグループを挙げてDXに取り組み、2024年5月には経済産業省が選定する「DXグランプリ2024」を受賞した。多岐にわたる事業を展開し、長い歴史を持つ巨大組織がどのようにDXを推進してきたのか? 2025年3月6日にビジネスエンジニアリング(B-EN-G)主催の年次イベント「BE:YOND 2025」で語られた基調講演(KEYNOTE2)の内容から、製造業DXの現状と未来に迫る。

講演者
三菱重工業株式会社
デジタルイノベーション本部長
田崎 陽一 氏
株式会社INDUSTRIAL-X
代表取締役 CEO
八子 知礼 氏
ビジネスエンジニアリング株式会社
代表取締役社長
羽田 雅一
講演タイトル
「製造業のDX最前線 ~DXグランプリ2024を受賞した三菱重工流DXとは~」
三菱重工業株式会社は、"DXでデジタル技術とものづくりを「かしこく・つなぐ」"をコンセプトとしてグループを挙げてDXに取り組み、2024年5月には経済産業省が選定する「DXグランプリ2024」を受賞した。多岐にわたる事業を展開し、長い歴史を持つ巨大組織がどのようにDXを推進してきたのか? 2025年3月6日にビジネスエンジニアリング(B-EN-G)主催の年次イベント「BE:YOND 2025」で語られた基調講演(KEYNOTE2)の内容から、製造業DXの現状と未来に迫る。
多様な事業ドメインの強みを結集し、価値を提供していく

三菱重工業におけるDXの背景について、三菱重工業株式会社 デジタルイノベーション本部長の田崎 陽一氏は、「変化し続ける社会への価値提供」をポイントに挙げ、「国内外における社会情勢の変化、エネルギーの転換や国際関係の悪化、物流問題、エネルギー問題といった課題に対し、痛感するのは人手不足です」と説明する。
さまざまな社会情勢の変化に伴い、開発やものづくりを担う人材が不足しており、課題解決のためには自律化、自動化を可能にするソリューションが求められている。そこで、同社では、多様な事業ドメインの強みを結集、組み合わせて価値を提供していく方針だ。
同社の事業ドメインは大きく4つあり、火力発電所用のガスタービンや原子力発電プラント、航空エンジンなどを担う「エナジー分野」、CO2回収プラントや新交通システム、製鉄機械などの「プラント」、フォークリフトや自動車エンジンのターボチャージャー、エアコンなどの「物流・冷熱・ドライブシステム」、そして、「航空・防衛・宇宙」領域だ。田崎氏は「これらの事業の集合体を三菱重工の強みと理解しています」と話した。
また、同社は国内にとどまらず、海外にも多くの事業所や工場を展開している。海外に製品を提供するにあたっては、グローバルでさまざまな制約があるが、それも含めて、同社の強みだという。
これらの強みを結集して、さらなる顧客価値を提供するため、DX推進部門として、2022年にデジタルイノベーション本部が設立された。田崎氏は「プロセス変革や体験価値向上、製品の強化、新規事業創出などを通じて、ITとOTが融合するイノベーション実現に向け改革を進めていくのがミッションです」と説明した。
「デジタルソリューション基盤を整備し 非競争領域は標準化を進める
三菱重工業は、さまざまなエンジニアリング、製品を通じて、独特のノウハウを束ねてきた。例えば、ITソリューションの標準ツール化や、プラントのロジックを他製品に活用する「プロダクトの展開」、機械同士の協調による「エコシステム化」、国家プロジェクト、重要インフラを担うノウハウを結集し、安心・安全な製品、ソリューションを提供する「セキュリティ」などだ。
しかし、田崎氏は「ITとOTの連携不足が課題となっています」と話す。そこで、同社は新たなソリューション体系「ΣSynX」(シグマシンクス)を整備し、価値創造プラットフォームとなるデジタル基盤を構築。物流自動化、CO2回収効率化、カーボンニュートラル電力供給など領域を問わずに活用できるデジタルソリューションを展開している。
さらに、「ソフトウェアの部品化・標準化による共通基盤の確立」や、シームレスなデータ活用による「業務プロセス変革」を進めている。さらに、ERP導入時に社内に業務プロセスが変わることの抵抗がある点を考慮し、「標準化は強制せず、会計や調達といった非競争領域に絞って実施しています」と田崎氏。そして、販売やアフターサービス、IoT、サプライチェーンといった領域は、事業における競争領域のため、「自分たちで変革を推進してもらうのが基本的な考え方」と述べる。
実機とシミュレーション技術を組み合わせた7つのDX事例
続いて、田崎氏は、実機とシミュレーション技術を組み合わせたDX事例について紹介した。
1つ目は「稼働中のガスタービンの目標出力に対して制御を最適化した事例」だ。稼働中のガスタービンの目標出力に対して制御を最適化するため、稼働中の圧力・出力・温度などの観測データを活用し、挙動と性能の関係を解析。田崎氏は「この技術自体は20~30年前から存在しており、当時は古いプログラム言語で運用されていましたが、今回、モジュール化技術によって再構築しました」と語る。
2つ目は「AIを用いて専門性が高い判定を自動化、効率化した事例」だ。表面材料の分析検査にディープラーニングを活用し、従来は人間が判定できなかった検出を可能にした。田崎氏は「重要なのは、最新技術に頼るのではなく、ExcelマクロやFORTRANといった過去の資産を活用し、デジタルイノベーション部門がITの力で実装可能な形に変換することです」と強調した。これにより、効率化を実現しながらDXを推進した。
3つ目は「スマート巡回点検システム」の事例で、モバイル技術を活用し、設備内のポンプ異常を自動検知する仕組みを導入した。従来は専門の設備管理チームが毎日点検していたが、このシステムにより点検作業が省人化されている。
4つ目は「MRグラスを活用した組み立て効率化」の事例だ。ボイラー機器の据え付け、組み立て作業において、従来はチョークを使って配置や接続位置を記していたが、MR(複合現実)グラスを活用することで、技術的な指示を視覚的に表示し、作業をデジタル化した。これにより、従来の手書き作業がほぼ不要となり、作業負担が97%削減されたとのことだ。
5つ目は「オペレーションの最適化事例」だ。ゴミ焼却装置において、焼却状況やゴミの種別を画像や音、温度データを活用して分析。異常な物質の混入や燃焼異常を自動的に検知し、運用の最適化を実現している。
6つ目は「次世代制御室モデル」の事例だ。複数の製鉄生産ラインを一元監視する「セントラルコックピット」を導入し、トラブル時の迅速な対応とリカバリーを実現。単なる監視システムではなく、レイテンシー1秒以内でデータを処理し、各装置のIoTデータをリアルタイムで取得し、モニタリング状況は録画され蓄積されている。「収集したデータはトラブル発生時に過去の事例の振り返りや、将来の解析にも活用できる点が特徴です」と田崎氏は説明した。
7つ目は「遠隔監視・状態予測・エネルギー最適化モデルの展開」事例で、サービス事業の収益を支えるデジタルツールを、ビジネスモデルとともに他分野に応用する取り組みだ。例えば、大量のカメラ映像を遅延なく取り込むOT技術を活用して、艦船の集中監視や交通システムの情報管理へ応用。また、ガスタービンや火力発電プラントでは、遠隔監視により異常検知や予備品交換の最適化を実現した。さらに、クラウドアプリや時系列データを活用することで、CO2回収装置の制御や生産設備のエネルギー最適化を推進するなど、新たなビジネスモデル創出につなげている。
「これらの取り組みは、完璧なデジタル基盤を整備するのではなく、まず既存のデータを蓄積し、活用することから始まりました。特に重要なのは『チェンジマインド』『教育』であり、ITとOTの融合が生み出す価値を理解することが鍵となるでしょう。そのために、2~3万人の社員を対象に教育プログラムを実施し、eラーニングなどを通じてデジタル技術の理解を深めています。DXの成功には、経営層・管理職・現場の3層すべてに対してメリットを提示し、納得感を持たせることが不可欠です」(田崎氏)
競争領域は現場のビジネス部門が担い 非競争領域は会社側が標準化の仕組みを用意
 田崎氏の話を受け、株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役 CEOの八子 知礼氏は、「シグマシンクスの由来」について尋ねた。田崎氏は「シグマは総和、シンは連携、X(クス)は未来の意で、三菱重工がこれまで培ったものを連携させ、未来に向けて価値の総和を拡大、最大化していくとの思いが込められています」と紹介した。
田崎氏の話を受け、株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役 CEOの八子 知礼氏は、「シグマシンクスの由来」について尋ねた。田崎氏は「シグマは総和、シンは連携、X(クス)は未来の意で、三菱重工がこれまで培ったものを連携させ、未来に向けて価値の総和を拡大、最大化していくとの思いが込められています」と紹介した。
続いて、八子氏は「ITとOTを連携させるには、カルチャーも異なり、社内に反発があったのでは?」と質問。田崎氏は「反発は未だにあり、そこを打破しようと日夜取り組んでいます。ITとOTは、それぞれ異なる文化を持つため、統合には課題が多いです」と回答した。
企業内では、部門ごとに異なる視点を持ち、それぞれの専門領域に閉じこもりがちだ。しかし、デジタル化を進める中で、異なる分野の技術が互いに活用できることに気付くケースが増えており、その共通点の1つが「セキュリティ」だ。
これは発電プラント、防衛、物流、交通システムなど、あらゆるインフラにおいて重要視されていることから「セキュリティを軸に統合を進めることで、異なる分野の関係者が共通の視点を持ち始めることができました」と田崎氏は言う。
また、「標準化と部品化」も統合の重要な要素の1つだ。三菱重工の取り組みでは、完全に統一したシステムではなく、既存のツールを生かしながら柔軟に適用できる標準ツールを開発。標準ツールを活用することで、ITとOT双方の相互理解を進め、現場とデジタルの融合が進みやすくなるとのことだ。田崎氏は、「異なる文化を持つITとOTの統合には、共通の基盤と理解を広める工夫によって、なるべくイメージしてもらいやすくすることが重要です」と述べている。
さらに、八子氏から「標準化と競争領域のバランス」について問われた田崎氏は、製鉄業における画像解析やAI技術の活用事例を引き合いに「製鉄のロールの異常検知にAI技術を活用する際に、標準化された部品を使うことで効率的にシステムを構築することが可能です」と説明した。しかし、標準化されたパーツだけでは次の展開に進むことが難しいと田崎氏は話す。
「標準化された部品を活用してどんな価値を創出するかは、ビジネス部門独自のクリエイティブな領域です。標準化されたツールを使いながらも、それをどのように活用するかは各工場の判断に委ね、工場ごとの独自の創意工夫を促すことが重要です」(田崎氏)
工場の改革の担い手はビジネス部門側であり、競争領域は自分たちで作り、非競争領域は標準化の仕組みを会社側が用意するという役割分担が大事で、「お仕着せの変革では意味がない」ということだ。
教育と人材育成で標準化を推進
その後、ビジネスエンジニアリング株式会社 代表取締役社長の羽田 雅一から、「先ほどご紹介いただいた先進事例を担うAI、IoTを使ったDX部隊と、既存の基幹システム、インフラ、セキュリティを担当する部隊が、全て田崎氏の傘下にありますが、この組織機構は会社としての相当な判断があると思います」と田崎氏に尋ねた。
この問いに対して田崎氏は、「IT領域の人材は豊富にいる一方で、OT領域の人材は事業部に密着しており、全社的な統合が難しい状況です」と話し、「特に、OT領域の人材を他の部門へ配置換えをするときには、事業部との連携や品質保証の確保など、複雑な調整が求められます。そのため、各事業部門とは事業部で蓄積したノウハウを全社の取り組みに活用することで費用を割り振るなどの調整を行いました」と述べた。
さらに田崎氏は、教育と人材育成が重要な役割を果たすと強調する。ITの知識を持つ人材がOT領域にも理解を深め、逆にOTの専門家がITの基礎知識を習得することで、「標準化や共通化の理念を共有し、全社的な協力体制を築くことができます。その結果、限られた人材リソースを最大限に活用することが可能となります」と話す。
その後、トークテーマは、「継続的な技術蓄積」に移る。八子氏から「会社にいるベテラン社員は、熟練すればするほど“自分の標準”を持っているが、そうしたノウハウの活用についてどう考えるか」について問われた田崎氏は、「長年の経験を持つベテラン社員が引退を迎える際、その技術やノウハウを次世代に引き継ぐことが重要です」と述べる。
また田崎氏は、自身の技術や標準が企業の基準として残ることはベテラン社員にとってのモチベーションにつながると言う。
「AIやデジタル化の進展により、これらのノウハウをデータ化して保存し、組織全体で活用できる仕組みを作ることが求められています。退職後もその技術が企業に残り、次の世代に引き継がれるというメッセージは、その先に、お客様に価値を届ける、ひいては社会に価値を残せるというメッセージを会社として発することにもつながります」(田崎氏)
「現場の思い」がデジタル化され、会社に生き続ける
 最後に、羽田から「DXグランプリ受賞の決め手は何だと思いますか?」と問われた田崎氏は、「シグマシンクスが掲げる4つの要素、標準ツール・プロダクト・エコシステム・セキュリティという当社の強みと、標準化にフォーカスした点が評価されたのではないかと思います」と話し、こう続ける。
最後に、羽田から「DXグランプリ受賞の決め手は何だと思いますか?」と問われた田崎氏は、「シグマシンクスが掲げる4つの要素、標準ツール・プロダクト・エコシステム・セキュリティという当社の強みと、標準化にフォーカスした点が評価されたのではないかと思います」と話し、こう続ける。
「ただし、DXの取り組みはまだまだクリエイティブな価値創出までには至っていない状況です。機械同士がソフトウェアで協調し、CO2排出削減や物流最適化などの分野で価値を生み出していけるように取り組みを進めていきたいです。また、今回の受賞で、DXに向けた社内の雰囲気は前向きなものに変わってきました。当社は匠の技術を持った技術者が多く在籍しますが、AIの台頭でベテラン社員が保有するノウハウが会社にデータ化され、蓄積される世界の実現が現実化してきました」(田崎氏)
これは、社員が生き生き働く世界と直結していると考えており、「現場の思いをデジタルで残し、会社に生き続ける」というメッセージを発せられるような経営ができれば、素敵だと思う──、田崎氏はこのように締めくくった。

BE:YOND 2025レポート
「BE:YOND 2025」イベントレポート詳細はこちら