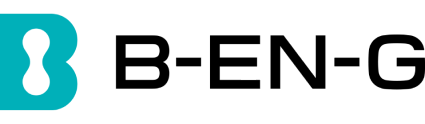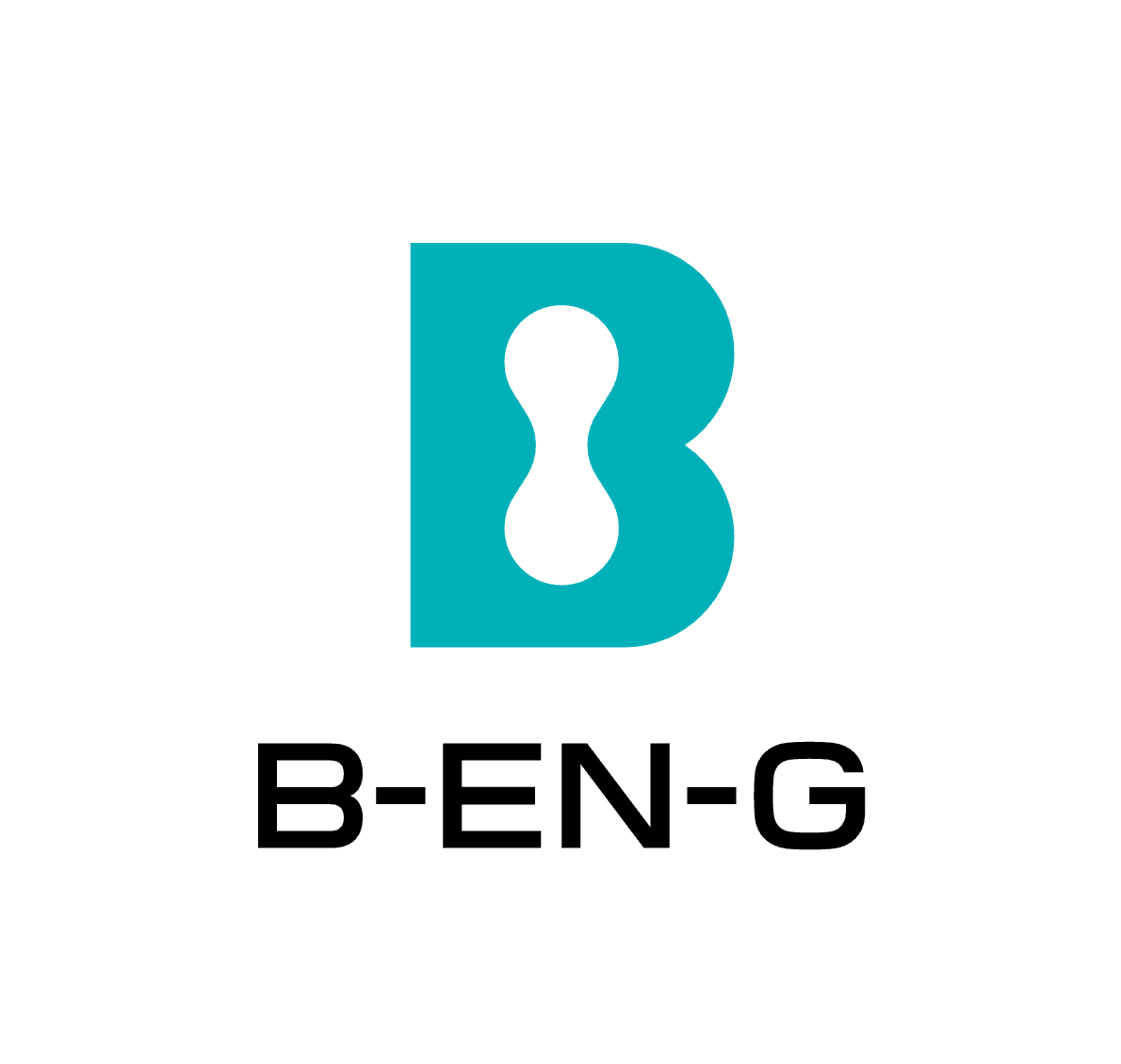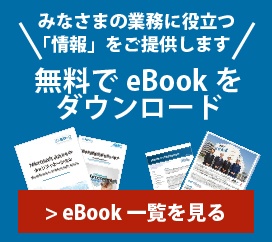BE:YOND 2025 セッションレポート「経産省が解説。製造業が向き合うデジタル、グリーン、経済安保」

講演者
経済産業省 製造産業局 総務課 課長補佐(総括)
大臣官房 政策企画委員(製造産業局担当)
河野 孝史 氏
講演タイトル
「製造業をめぐる現状と課題 今後の政策の方向性」
製造業の事業環境が大きく変わる中で、どのような方針を立てて、直面するさまざまな課題の解決を図るべきなのだろうか?その道筋を示すのが、2024年5月に経済産業省が公表した報告資料「製造業をめぐる現状と課題 今後の政策の方向性」だ。2025年3月6日にビジネスエンジニアリング(B-EN-G)主催の年次イベント「BE:YOND 2025」で語られた基調講演(KEYNOTE4)の内容を踏まえ、このレポートの要旨を解説する。
日本の経済と製造業の現状

BE:YOND 2025を締めくくる、KEYNOTE4の講演には、経済産業省 製造産業局 総務課 課長補佐(総括)の河野 孝史 氏が登壇した。製造産業全体の政策の企画・立案・執行などを担当している河野氏は、製造業を巡る現状と課題について現政権がどう認識しているのか、そして製造業のDXについて、どのような政策を考えているのかを紹介した。
河野氏は最初に、日本のマクロ経済の現状について言及した。日本は貿易赤字が拡大している一方で、第1次所得収支が伸びている状況にある。政府としては、こうした状況を踏まえ、国内投資を重視する方針だ。
その理由の1つは、日本とドイツの違いから浮かび上がってくる。潜在成長率を分析すると、技術進歩などの要因に大きな差は見られないが、資本投入量(=国内投資)の推移を比較したデータでは、ドイツが堅調であるのに対し、日本は2009年から前年度比マイナスとなっているのだ。
河野氏は次に、潮目が変化している動向として、「30年、40年というスケールで見ると、設備投資と人材投資の両面で、目標値も含めて明らかな変化が見られます」と説明。企業の設備投資は過去最高水準の伸びを継続しており、2024年度の設備投資計画は前年度比で10%増(2024年12月現在)と、民間企業の積極的な姿勢がうかがえる。また、賃上げ率は30年ぶりの高水準を取り戻している。
ここからは、製造業に関する説明が展開された。まず前提として、GDPと1人当たりの賃金水準のデータを基に、製造業が日本経済の中で突出した存在感を示していることを改めて示す。「製造業は雇用者1人当たりの賃金水準が比較的高く、日本経済の発展や雇用の確保の観点から、引き続き重要な産業です」と河野氏は強調した。
一方で、日本の製造業には課題もある。「稼ぐ力」だ。主要500社の財務データを日米欧で比較すると、日本企業の純利益率とROE(株主資本利益率)は、欧米企業に大きく水をあけられている現状が浮き彫りになる。河野氏は「日本のROEは、欧州と5%程度、アメリカとは10%程度の差があるということを認識しなければなりません」と語り、危機感を共有した。
加えて、主要製造業企業の海外売上比率と利益率にも言及する。日本の主要メーカーにおける海外売上比率は2014年にアメリカを上回り、現在50%を超えているが、利益率は企業によってさまざまである。河野氏は、「グローバルに事業を展開すればするほど、現地の事情に応じた意思決定が難しく、海外展開を進める上での課題となっています」と認識を示した。
GX・経済安全保障を巡る動向
河野氏は続いて、製造業を巡る課題についての認識を示した。
「製造業全体として共通する政策課題もあり、ここ数年では、GX(グリーントランスフォーメーション)、DX、経済安全保障の3つが、製造産業政策として業を超えて横断的に対応しなければならない課題だと認識しています」
GXに関しては、製造業の中でも特に鉄鋼、化学、紙パルプ、セメントなど、いわゆる重厚長大型産業がCO2排出量の多くを占めており、政府は製造プロセスやエネルギーの転換を支援している。例えば、GX移行債などの新しいスキームを活用し、5年間で5000億円規模の設備投資支援を進めている。
また、GX産業につながる市場創造に向けた取り組みも行っている。GXで生み出された環境配慮型の製品を普及させようと、政府調達基準の設定や、グリーンに特化した製品導入の補助金上乗せなどを実施してきた。一例として、関係省庁で連携し建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けて、建材のCO2基準などを検討している。また経済産業省ではクリーンエナジービークル購入時の補助金(1台当たり最大85万円)に、環境配慮型の鉄を使用した車の場合は5万円を追加することで、需要のより一層の喚起を進めている。
一方、経済安全保障の面で河野氏は、米中の輸出管理措置合戦が激化していることに言及。中国は2023年8月、ガリウムとゲルマニウムの輸出管理を強化し、実際に日本の輸入量が相当量減少するなどの影響があった。製造業各社においては、自社が仕入れる製品あるいは販売する製品が、中国産の鉱物とどのように関係しているかを改めて確認する機会となった。
そして経済産業省は、特定国依存を回避したサプライチェーンの構築に向けて動いてきた。昨年夏には、製造産業局内に「サプライチェーン強靱化政策室」を新設し、鉱物のサプライチェーン多角化に向けた予算措置や、企業への情報提供支援など、さまざまな施策を講じているところだ。河野氏は「他国情勢やサプライチェーン全体像など、政府が有する情報を企業に積極的に提供し、サプライチェーン全体で取り組む方策の検討を促しています」と話す。
さらに河野氏は、米国政府の関税などに関する相次ぐ発表に触れながら、交渉を引き続き行いつつ、その影響の精査や国内の産業・雇用への支援などを適切に行うことが、経済産業省が直面している課題であると述べた。
ここまでが現在、製造産業政策として業横断的に共通の課題認識の下で進めている、DX以外の主な政策についての説明だ。
製造業DXにまつわる経済産業省の方向性
 講演の後半で河野氏は、日本の製造業がDXにおいて遅れをとっている現状を踏まえ、経済産業省としてどのような政策対応を進めているのかについて説明した。
講演の後半で河野氏は、日本の製造業がDXにおいて遅れをとっている現状を踏まえ、経済産業省としてどのような政策対応を進めているのかについて説明した。
河野氏はまず、なぜ「デジタル敗戦したのか?」をテーマに、政策の前提となる課題認識を共有した。国際的な競争力ランキングにおいて、日本が恒常的に低い位置にある原因として、「現場任せ」、「コーポレートの不在」が大きいのではないかというのが政府の見解だ。その上で河野氏は、グローバル競争に勝ち抜くためには、ビジネス面での強化だけでは不十分であり、コーポレート機能の強化が不可欠だと強調する。
製造産業局では「CX(コーポレート・トランスフォーメーション)」という概念を提唱し、さまざまな議論や発表の場を設けてきた。例えば、グローバル競争力強化に向けたCX研究会を立ち上げ、報告書を取りまとめて公開している。その中では、グローバルカンパニーの中でコーポレート機能をどのように持つべきなのかを整理しており、ファイナンス、HR(人的資源)、デジタルに関して、経営課題あるいは企業のパーパスとすり合った状態で、現場にも納得性の高い状態で浸透させていくための方策を示している。
続いて河野氏は、日本企業のDX活動内容を整理し、その多様性について説明した。「DX」という言葉は多義性があるため、ともすればアナログをデジタルに変えるだけでDXと称することも少なくなく、経済産業省が選定に関わる「DX銘柄」の中にも、そうしたものが散見された。
「一言で申し上げれば、現場の一部のアナログ作業をデジタル化した、あるいはある特定の部分を自動化したような事例を、DX事例としているものが、約9割です。対して、経営に関するDX、すなわち、コーポレート機能を強化し、特定のビジネスだけではなく経営全体の刷新における、デジタルのパワーの最大限活用はまだ1割でしかありません。ここを強化していくことがポイントだと考えています」
そしてこの課題に対し、製造産業局では2つの政策の方向性を打ち出している。1つは「個社のDX」、もう1つは企業間のDXである「企業間のデータ連携」だ。
個社のDX~部分最適から全体最適への転換を促進
個社のDXでは、部分最適から全体最適への転換が必要である。解決したい経営課題や業務変革課題の特定がないままに、DXに着手してしまうと、課題解決に寄与しない、既存の業務・部門の範囲にとどまる業務の最適化となるケースが大半だ。PoC(概念実証)で終わってしまうケースもある。厳しい表現だが、この部分最適のDXを「失敗」と呼ぶことにする。では、どのような流れで取り組めば「成功」と呼べるDXを実現できるのだろうか。
「まず経営課題を特定します。具体的に何をどこまでやるのか、何をやらなくてもいいのか、ということまでを含めて経営層がコミットし、問題意識を具体化することが重要です。この際、現場の末端社員まで含めて理解が浸透するよう、いかに言語化し、繰り返し共有していくかが大事だと考えています」
その上で、データの標準化・一元管理を実現することによって全体最適を目指す。部門・業務ごとにデータを個別管理している状態では、経営層の課題解決につながるような活動が難しいため、部門をまたがった共通のシステムあるいはデータ基盤を作るのだ。
この転換の取り組みを支援するため、経済産業省は「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン」を策定。DXを進める上での議論では、「何から考え始めるべきなのか」、「論点が網羅されているのだろうか」といった疑問が生じることを想定し、7つの観点から課題を整理している。河野氏は、「必要な論点の全てを確認したことや、経営層も含めた課題を特定したことを確かめる必要があります。このガイドラインは、そのための地図のようなものです」と説明する。
加えて、経済産業省では「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」も取りまとめた。これは経営課題としてデータの利活用を進めている中で、さまざまなAIシステムを利用する場合に、どのデータを提供してよいのか判断に迷う企業が多いためだ。AIサービスの規約をどのように読み込めばいいのか、自社の競争力に関するデータが流出しないのか、といった具体的な課題が経済産業省に寄せられたため、弁護士の協力も得て作成にあたったという。
さらに、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて、製造業向けデジタルソリューションの懸賞金事業「NEDO Challenge,製造業DX」を3月中旬から公募予定だ(※2025年3月18日から開始している)。募集テーマは、「製造技能の伝承に関するデジタルソリューションの開発」、「新たな製造ノウハウの構築に関するデジタルソリューション開発」の2つを設定している。この事業の背景について河野氏は次のように説明する。
「まだ人の『経験と勘』に頼っており、その後継者もいないばかりか、そもそも伝承する技能の定義すらできていない製造事業者も存在している中で、その課題を解決に導きたいという問い合わせが多く寄せられていました。製造業が伝統的に持っているが、アナログあるいはそれを言語化できないような、日本のもの作りの強さをデジタル化して、日本としてそれを大切にし、後継に託していくことが、日本の製造業の競争力確保のために極めて重要と考えています」
企業間データ連携~業界横断のDXを促進
政策のもう1つの柱である「企業間データ連携」では、法改正によってIPA内に新設した「デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)」の活動が紹介された。経済産業省は、DADCやNEDOとともに、運用および管理を行う者が異なった複数の情報処理システムを連携する仕組みに関して、アーキテクチャの設計、研究開発・実証、社会実装・普及の取り組みとして、「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステム)」を立ち上げている。
「新しいビジネスを考えたときに、例えば『スマートシティは何省の何課が所管なのだろうか?』といった疑問が出てくるでしょう。そこには土地利用、警察、モビリティ、医療や介護といったさまざまな観点が含まれます。そうしたさまざまな規制やプレイヤーが存在する中でワークするためのイニシアティブがウラノスであり、多様な業界(政府、防災、教育、医療、金属、素材、エネルギー、自動車など)の横断的なシステム連携の実現を目指しています」
ウラノスの取り組み事例として河野氏が紹介するのは、「自動車・蓄電池業界横断的なデータ連携の基盤構築」である。これはどの自動車の中にどのような蓄電池があるのか、あるいはそのリサイクルの過程を共通管理するトレーサビリティ基盤だ。業界標準とするために、自動車のほぼ全てのOEMメーカーが関与して一般社団法人を作った上で、政府が公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定を付与して、公的・中立な性質をさらに高めている。
「欧州の規制に対応するには、国内で蓄電池のサプライチェーンを構築しておく必要がありました。このトレーサビリティ基盤によって、市場の拡大につなげていきたいと思っています。また、経済産業省としてはこれをさらに経済活動全体を支えるプラットフォームへ拡大していきたいと考えています。製品・サービスでは、蓄電池だけから自動車全体、さらに化学物質管理や資源循環といったところまで拡大させ、経済活動では、物の流れだけではなく、商流、金流、人流にまでつなげていきます」
最後に河野氏は講演を振り返った上で、「個社DXでは、ご紹介した『スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン』、『AI契約チェックリスト』、『懸賞金事業』の活用をぜひご検討いただきたいです。また、企業間データ連携では、DADCやウラノスのユースケース創出に製造産業局として力を入れていますので、産業データ連携に関心のある方はご相談いただければと考えています」と呼びかけた。

BE:YOND 2025レポート
「BE:YOND 2025」イベントレポート詳細はこちら